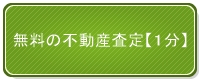不動産買取に外せない
 |
併用しないと損
 |
最後の相見積もり
 |

不動産をお持ちの方は、一軒ずつ直接業者とやり取りをすることも大切ですが、一度インターネットの無料見積もりを取ってみられることを強くおすすめいたします。不動産業者と取引をする際にも、自分の資産が、一体最大でどれくらいの値がつくのか、を客観的に把握していることで、多くのカラクリを見破ることが出来るようになり、損をしない取引が実現可能です。
土地・物件は例え、どんな状態・場所にあろうとも大切な資産です。潰して新しくすれば良いと一概に決められるものではありません。損せず、賢い取引を行っていただければと願う次第です。
不動産仲介会社の価格査定は当てにならない
不動産の売却をする際、一般的には地域の不動産事情に詳しい不動産仲介会社に依頼し、その不動産の価格査定を依頼することから始めます。それを考慮し、近隣相場や売主の希望などを踏まえたうえで「売り出し価格」を決めます。しかし、そのように仲介会社が提示した額は、当てにならないことが多いのです。
仲介会社に、「この辺りの取引相場は坪50万円です。ですから売り出し価格は坪55万円くらいが妥当です」と、事例をたくさん見せられながら言われたら、「事例を見てもそうだし、不動産の取引相場をよくわかっているプロが言うのだから、間違いないだろう」と、「専門家の意見」に妙な説得力を感じるかもしれません。しかし、本当にその価格が適正だとは、決して断言できないのです。
私自身、これまでたくさんの不動産の価格査定を行いました。その中で査定価格と最終的な売却価格が一致したことは、ほぼありません。坪55万円と予測していた価格が坪62万円まで伸びたり、坪130万円と予測していた価格が146万円まで伸びたりすることが度々起こるのです。
なぜ、このような差異が生じるのでしょうか。それは「この土地が絶対欲しい」と思う買主のモチベーションによって、売却価格が変わるからです。買主の購入に対するモチベーションが高ければ高いほど、高い買値を提示してくれるでしょう。いわば、買主の「本気度」によって、不動産の価格は大きく異なるのです。
では、そのような買主の「本気度」を「価格査定」に反映できるのでしょうか。実際、そのような特殊事情を価格査定に反映するのは困難です。あくまで一般的、平均的な近隣取引事例、相場価格をもとに「価格査定」を行うことになります。ですから、その「価格査定」を参考にするのは有益なことですが、鵜呑みにするのは大変危険なのです。
相場と時価は違う
不動産の売り出し価格は、仲介会社など不動産のプロのアドバイスや相場価格、近隣取引事例をもとに決められます。アドバイスする側はもちろん、適正な価格を見極めようとします。ただし、この「相場価格」というのは、心を惑わす価格であるため注意が必要です。
「相場価格」で売れると、売主としては何となくほっとするかもしれません。「損をしなかった」「正な価格で売ることができた」と嬉しくなるかもしれません。しかし、この「相場価格」で売れたことを、素直に喜んでいいのでしょうか。私はこの「相場価格」に常日頃から非常に疑間を持っています。
不動産を売る相手は一人だけです。たとえば100カ所、200カ所を相手に売るなら、平均的な金額、すなわち相場価格に落ち着きそうです。しかし、もし1カ所しか売らないのであれば、本当に「平均的な価格(=相場価格)」で売ることしかできないのでしょうか。
実際に不動産を売却する時には、国税庁が定めた「路線価格」で売るわけでも、不動産鑑定士が定めた「鑑定評価」で売るわけでも、近隣取引相場から定めた「相場価格」で売るわけでもありません。その瞬間に最も高値をつけてくれる「たった一人」に売ればいいわけです。
わかりやすい例として、「まぐろの競り」を例にしてみましょう。築地では、毎年年始に「まぐろの競り」があります。2013年の築地の初競りでは、大間産のクロマグロが1億5540万円(1kgあたり70万円)で有名寿司チェーン店に競り落とされました。
これまで過去最高だった2012年の5649万円(1kgあたり21万円。落札者は同じ)の実に3倍近くとなり、記録が残っている1999年以降、最高値となったようです。この2013年の初競りで落札したクロマグロは、大トロで1貫あたり398円でお客さまに提供したそうですが、原価から考えれば1貫あたり1万円を軽く越えたようです。
すなわち、この落札価格は原価率や利益率をもとに決めたものではないようです。では、このクロマグロの「相場価格」は一体いくらなのでしょうか。1億5500万円前後なのでしょうか。それとも2012年の落札価格である5600万円前後なのでしょうか。おそらく、平均的な取引価格から算出した金額を「相場価格」とするなら、もっと安くなるはずです。
しかし、「時価は?」と聞かれたらいかがでしょうか。この場合、実際に1億5540万円で取引された以上、「時価は1億5540万円」ということになるのではないでしょうか。このように、「相場価格」は説明がしやすいですが、「時価」は説明が困難なものだと私は思っています。
実は、不動産にも信じがたい価格がつくことがあります。原価率や利益率を考慮すると、割に合わないはずの価格がつくことが度々起こるのです。では、どんな時に、コ日通に考えたら説明できないような価格」がつくのでしょうか。それを知っておくと、今後の役に立つでしょう。
先に答えをお伝えすると、まず挙げられるのは、駐車場や農地など、「戸建やマンションが分譲できる土地」です。不動産の売買は、「心理戦」です。売却を成功させたいのであれば、買主の心理を深く読み解くことが必要となります。その際に意識しておきたいのは、不動産の買主が「個人」である場合と「会社」の場合とでは、それぞれ異なった心理が働くという点です。マイホームの購入など、不動産の買主が一般個人である場合、基本的には「個人の財布」からお金を出すことになります。
すなわち、自分の財布から毎月のローンを払っていかなければなりません。マイホームは収益を生むものではなく、自分の財布の中身が減る一方です。当然「少しでも安く買いたい」「無理してまでは買いたくない」というのが買主の気持ちです。つまり、不動産を手に入れるためにお金を余計に出すことに対して、消極的になりがちです。
一方、戸建住宅やマンションが分譲できるような大きな土地の購入などは、買主が会社であることが多いです。その場合、「会社の財布」をもって購入します。会社のお金で買うわけですから、もちろん仕入担当者個人の財布の中身は減りません。それどころか、購入した土地を分譲して収益が上がれば、担当者個人のお金は増える可能性があるのです。会社からは、ボーナスが支給されるかもしれないからです。
購入した事業用地の上に戸建住宅やマンションなどを建てて分譲することによって、最終的には会社も利益を得ることができます。つまり、会社の財布の中身も増えるわけです。結局のところ、担当者や社長、役員の「個人の財布」も「会社の財布」もその中身が増えるため、お金を出すことに積極的になります。
もちろん、より安く買えた方がより大きな収益が生まれるため、安く買いたいのは当然です。しかし買えなければ収益が上がらず、会社が倒産する可能性すらあるわけです。このように「会社の財布」で買う場合には、「個人の財布」で買う場合とは別の心理が働くことになるのです。
また、社長や役員などの様々な思惑が働く結果として、「この不動産を絶対に買う」という状況になることがあります。たとえば、次のような場合があります。「販売在庫がなくなってきたから、今回、無理してでも買いたい」「今回の決算で、どうしてもあと少し売り上げが欲しい」「この地域では、どうしても他社に取られたくない」このような状況では、買値が相場価格を大きく上回ることがあります。
ところが現実には、買主が「個人の財布」で買う不動産と「会社の財布」で買う不動産を同じように売ってしまっている傾向があります。何とも残念なことですが、これが日本の不動産売却の現実なのです。
「餅は餅屋」のウソ
「餅は餅屋」という言葉があります。「専門家に任せるのが一番」という意味です。不動産売却においても、売主としては「不動産売却の専門家に任せたら安心だ」と思いがちです。
しかし、必ずしもそうとは限りません。「不動産の専門家」と一口にいっても、不動産のあらゆる分野に精通していて、かつあらゆる分野で他を浚駕する強みを持っている不動産会社など存在し得ないからです。同じ不動産会社でも、「個人の買主を相手にするのが得意」「法人相手が得意」「マイホームの売却に強い」「事業用不動産の売却に強い」など、それぞれが得意とする分野はまったく違うのです。
特に注意すべきなのは、 マイホームではなく、事業用不動産を売却する場合です。なぜなら、売り方によって想像以上に価格差が生じやすいからです。時にはその差が2割、3割、4割以上にまで及ぶことがあります。その売り方の違いについては、一口に事業用不動産といっても、単純にひとくくりにはできません。その種類はいくつにも分かれます。
次のような種類に分かれます。
o住宅分譲用地(戸建分譲、マンション分譲他)
o収益物件建設用地(賃貸マンション、高齢者住宅他)
oロードサイド店舗用地
o物流。倉庫用地
o収益物件(木造アパート、鉄筋コンクリート造マンション、オフィスビル他)
このように「事業用不動産」だけで種類が分かれているのを見れば、「不動産の専門家」といってもすべてに精通しているわけではないということは、容易に想像できると思います。これらを売る時には、「必要な調査。準備」も「戦略」も「営業先」も「留意点」も異なります。
しかし、不動産仲介会社にもプライドがあります。自分が不得意な種類の不動産の売却を持ちかけられても、「その分野は不得意です。もっとその分野に強みを持っている人にお願いした方がいいのではないでしょうか」と売主に提案してくれることはなかなかありません。たとえ不得意な分野であっても、「頑張ります」と引き受けられてしまう可能性が高いのです。
それに対して、次のように反論する方もいるでしょう。
「依頼した不動産仲介会社が、売却する不動産の客付けに強い不動産仲介会社に持ち込めば、問題ないのではないか」なるほど、正論のようにも思えます。しかし、現実的にはそれが難しいのです。依頼された仲介会社はおそらく、売却を依頼された不動産に強い仲介会社を探すために、知り合いの数社に声をかけることになるでしょう。
しかし、もしも知人内という狭い範囲のみに働きかけるだけだとすれば、本当に高値を出せる最も良い買主を見つけることができるのか、疑間を覚えずにはいられません。また、不動産の売却では「誰が仕切るか」がすごく重要です。残念ながら、売却を依頼した仲介会社の方が「仕切り方」を誤る可能性もあるのです。
映画でもテレビでも、誰がプロデューサーを務めるかで作品の出来が全然違います。プロデューサーは全体を仕切るので、誰に、どのように動いてもらえば全体が最も上手くいくのかを真っ先に考えなくてはいけません。つまり、「全体像が見える人」「必要に応じて人を的確に動かせる人」がプロデューサーとして機能するわけです。
もしもプロデューサーが「全体像」が見えていなかったり、「誰にどう動いてもらったらいいか」がわかっていなかったらどうなるでしょうか。もちろん、良い作品は生まれません。同じように、不動産売却においてもプロデューサーの腕が悪ければ、良い結果は生まれません。
それを防ぐためにも、はじめから売却する不動産の特徴をよく把握し、状況に応じたプロデュースができる仲介会社に依頼することをおすすめします。
売主と買主の関係
不動産取引は「交渉」です。売主は「少しでも高く売りたい」「たくさんの人に検討してもらいたい」「自分達に有利な条件で売りたい」と考えます。 一方、買主は「少しでも安く買いたい」「競争せずこっそり買いたい」「自分達に有利な条件で買いたい」と考えます。言っていることはまったく「逆」です。その状況で「交渉」を進めると、どちらの言い分が勝るのでしょうか。
基本的には「交渉」は立場が強い方が優位に立ちます。相手の立場が強く、こちらの立場が弱ければ、相手の条件をのまぎるを得ないかもしれません。いくらこちらが「こうしてほしい」と言っても、「それなら結構」と断られてしまったら交渉は成立しません。
ここで、弱い立場にいる人、強い立場にいる人を例えてみます。
多くの売主にとっては、不動産を売るという経験は人生に一度あるかないかの出来事です。つまり、経験がほとんどありません。そして不動産に関する知識や情報もあまりないというのが現実です。さらに、多くの場合、何かしらの理由があって売る場合がほとんどです。それは相続税の納税であったり、借入金の返済であったり、相続人で公平に財産を分けるためであったりします。つまり、時間に制約があり、精神的にもあまり余裕がない場合が多いわけです。このように、経験や知識、情報があまりなく、さらに時間的、精神的な余裕もあまりない状況と仮定するなら、立場が弱くなってしまう可能性があるということは頷けると思います。
買主が個人の場合、「人生で初めて不動産を買う」という人がほとんどです。その場合、経験や知識、情報があまりないという意味では売主と同じです。しかし違うのは、時間的、精神的な余裕です。「物件も価格も魅力的なら買いたい」という立場であればどうでしょうか。無理してまで、一昌値を出してまで買うでしょうか。「時間をかけて、ゆっくり探そう」というスタンスであれば、コ」の金額なら買いたい」と指値をしてくるかもしれません。ただ、取引における力加減のバランスはまだ取りやすいといえます。
買主が個人ではなく戸建分譲会社やマンションデベロツパー等のプロの法人である場合は、毎年のように何件も不動産を購入していることがほとんどです。したがって、不動産取引の経験も知識も情報も、売主よりはるかによく知っているといえます。
一方、買主が「個人」であれ「法人」であれ、売主にとっては、売却する不動産を買ってくれる買主の存在はとてもありがたいものです。「ぜひ買わせていただきたい」と言われたら嬉しいものですし、ほっとします。売主の希望価格で買えるように一生懸命努力してくれるかもしれません。
しかしながら、不動産取引は「交渉」です。買主も「できるだけ安く買いたい」わけです。多くの場合、売主は売れないと困ります。しかも、早く売れないと困る場合も多いわけです。そのような状況であれば、買主が経験、知識、情報があまりない「個人」に対しても、経験も知識も情報も豊富な「法人」に対しても、あまり強い立場ではいられないというのは容易に推測できると思います。
つまり、仲介会社が売主側と、買主側のどちらの側に立って取引を進めるのかということです。ここが運命の分かれ道です。一般的に、仲介会社は、取引が成立しなければ、どれだけ動いても「無報酬」です。そうすると、「取引が成立すること」を優先せぎるを得ない傾向があります。では、「取引が成立すること」を優先したとすれば、その仲介会社は売主側と買主側のどちらに立った方が、取引が成立する可能性が高いのでしょうか。
結論からいえば、仲介会社は「売主」ではなく「買主」の側に立つことが多いのです。
それはなぜでしょうか。
そもそも不動産取引においては、買主側が「買う」と言わない限り、契約は成立しません。契約が成立しなければ、仲介会社には1円もお金が入ってきません。売主と買主との交渉では、以下のようなパターンが考えられます。
l 買主に、売主が提示している価格や条件を受け入れてもらう
2 売主に、買主が提示している価格や条件を受け入れてもらう
3 双方が歩み寄る(間を取る)
このように3つの選択肢がある場合、売主としては1の方向で話を進めることを希望します。しかし、買主には「できるかぎり安く買いたい」「自分達にとって良い条件で買いたい」という心理が働きます。そのため、あっさりと売主側の提示する価格や条件を受け入れないのが現実です。交渉を通して両者の希望を調整することになります。ここで仲介会社が恐れることは、買主に「こちらの条件を受け入れてくれないなら、他の案件を検討するので、この不動産の購入はやめます」と言われることです。
すると仲介会社は「では、売主の方に交渉してみましょう」と、2の方向性で取引を進めようとしす。つまり、売主に譲歩してもらおうとするのです。そして売主を説得しようとします。なぜなら、買主より売主の方が説得しやすいからです。
「希望者がたった一人しかいない場合」はさらに厄介です。購入希望者がたくさんいれば、ただ一人の買主に「NO」と言われても、売主に価格や条件を下げるなどの譲歩を求めないかもしれません。他の希望者に売ればよいのです。しかし、買主が他にいなければ、不動産仲介会社は「より高値で売ること」よりも、「確実に成約させること」を優先するかもしれません。
また、不動産の購入において、プロの法人である買主は仲介会社が紹介する不動産を何回も買ってくれることは意外に多いのです。しかし、売主が不動産を売ってくれるのは、ほとんどの場合一度限りです。すると仲介会社としては、売主よりも、何回も買ってくれる「お得意さん」である買主の方をより大切に扱うことになります。それを責めることはできません。そのため、買主の希望を優先して取引を進めることになる傾向があるのです。すると仲介会社としては、売主に条件を譲歩してもらえるよう、説得にかかってくるかもしれません。
仲介会社に、「この不動産は、前の道路が狭い」「駅から遠い」「周りの環境がよくない」「リーマンショック後、2割ほど価格が下がっている」「この買主を逃すと、1000万円以上損することになりかねません」「散々当たりましたが、今のところ他に良い買主はいません」と、ネガティブな面を並べて説明されると、売主は「ここで欲張って希望価格や条件に執着すると、取引が失敗するかもしれない」「譲歩したほうが確実に売却できるかもしれない」と納得して、価格や条件を下げてしまうかもしれません。
このように、売主と買主の間に立つ「仲介会社」が買主の側に立ってしまった時、売主が立場の弱く、買主が立場の強いとなってしまいます。売却するパートナーを選ぶ際には、売主側に立ってくれる仲介会社を選びたいものです。
普通の売り方では競争原理が働かない
何事も、競争があるから努力が生まれます。もしもこの世に受験がなければ、学生は一生懸命に勉強するでしょうか。もし、誰でも自動的に昇進・昇給できる仕組みであれば、 一生懸命に仕事に打ち込むこともないかもしれません。もしも誰でも意中の人と結婚できて、その幸せが未来永劫続くなら、相手を幸せにするために、自分を磨くために、日々努力をし続けることもないかもしれません。このことは、不動産の売却においても当てはまるのです。具体例で見てみましょう。
たとえば1億円の土地を売る時、通常買主は先着順で売主との交渉権を得ます。不動産取引は、一般的には、「相対取引」で価格が決まります。売主と買主が1対1で行う取引です。しかしながら、この売り方で売却価格を何割も上げることは難しいでしょう。なぜならこの売り方では、売却情報にいち早く気づいた買主が「1億円で買います」といえば、それ以上売却価格が上がりにくいからです。
もしも売主が複数の買主と同時に取引することができるなら、他の買主に、「1億円より高い買値を提示すればチャンスがある」と伝えることができます。すると「あちらが1億円で買うというのなら、こっちは1億1000万円出します」「それなら、こちらは1億1500万円まで買値を上げます」というように、競争原理が働くかもしれません。結果、設定した売値よりも高く売れる可能性は大いにあります。
しかし実際には、相対取引が原則です。つまり、はじめに設定した売り出し価格を基準に売却価格が決まるといえます。そのため、「この不動産は、もっと高く払ってもいいから絶対に手に入れたい」という人がいても、「この価格で買います」という人が先にいれば、交渉の余地はありません。
このように不動産売却は、売主にとっては圧倒的に不利といえる状況があります。このような現実の中で、相場よりも高く売るためには、 一体何をすればよいのでしょうか。
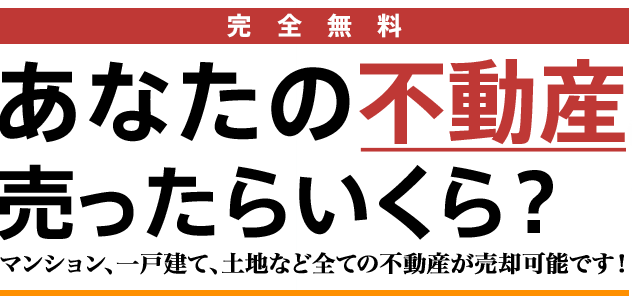
・ 不動産査定で、最も期待できるサイトです。ここで物件・土地の査定をすることで、その価格に驚かれるに違いありません。
・ 地方もカバーしていますので、日本全国どこでも査定可能です
・ 買取価格に自信があります。地元の不動産業者とは比較になりません

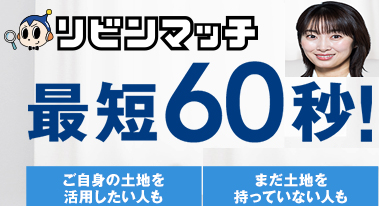
・ イエウールと同じように買取価格が相場より高い
・ 全国を網羅、どこでも参加できる
・ イエウールと相見積もりして、同じような価格が出た場合、より競争させて買取価格UPにつなげることが可能


・ イエウール、リビンマッチで納得がいかない時、第三の選択肢として試してみましょう